

1934 Official Short Wave Radio Manual
Complete Experimenters's Self Building and Servicing Guide
Joseph J. Carr 1980 First Edition, First Printing
Hugo Gernsback, Editor / H.Winfield Secor, Assoiciate Editor
Reprinted by Lindsay Publications Inc. 1987 ISBN 0-917914-64-3
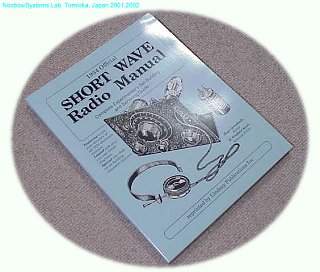
|
短い波
タイトルの
"Short Wave"
に注意してください。「短い波ラジオ」です。
1910年代、電波は地表面を這うようにして伝播するものであり、長距離無線通信のためには波長が長いほど有利で、
波長が300メートル以下の短い波はまったくの役立たずである。
だから、迷惑な素人無線家は200メートルより短い周波数に追いやってしまえ・・・
と、アマチュア無線は荒れ果てた、誰も住んでいない未開の領域に放り出されてしまったのです。
しかしそこでアマチュアが見たものは、たかだか数本の真空管と数10フィートのワイヤーアンテナだけで地球の裏側が聞こえてくる、摩訶不思議な世界。
やがて空高くにはヘビサイド・レイヤーと呼ばれる電離したイオンの層があり、
波長の短い電波はこれに反射して見通し距離をはるかに越えて伝わるということが明らかになると、ショート・ウェーブの大熱狂が起こります。
次々にショート・ウェーブの放送局が設立され、ラジオ部品メーカーも完成機メーカーもさまざまな新しい製品を送り出し、
アマチュアはありとあらゆる回路方式にチャレンジしていきます。
この本は、こうしたショート・ウェーブ・フィーバーの真っ只中の1934年に発行された
Official Short Wave Radio Manualのリプリント。
ショート・ ウェーブ受信機の組み立て記事を掲載していた雑誌、Short Wave Craft誌の集大成です。
市場に出回っているすべての最新モデルの回路図説明、受信機製作記事、技術解説がぎっしり詰まっています。
この後、"Short Wave" 「短い波」は、いつしか"Shortwave"「短波」 と呼ばれるようになります。
長距離無線通信は、まさにアマチュア無線家によって開拓されたのです。
|
|
百花繚乱
掲載されている短波受信機は、完成品も自作機もまさに百花繚乱。
使用されている真空管はすべて古典的なナス管またはST管で、短波での性能は良くはありませんでした。
が、性能を重視したセットはアルミシャーシやシールドケースを多用し、配線も極力短くするなど、高周波での安定動作への工夫が始まっています。
回路構成は1球レフレックスから、数本の真空管を使った再生式や超再生式、そして上位モデルではほとんどがスーパーヘテロダイン。
アメリカン・ボッシュ社のワールド・クルーザーなどは高周波1段・中間周波3段増幅のスーパーヘテロダインでオーディオ出力はプッシュプル、
トーンコントロールもあり。
つまみで4バンドを簡単に切り替えることができ、チューニングは横行きダイヤルで周波数が読め、
Sメーターもついているなどほぼ完成の域に達しています。
一方、既存の中波ラジオで短波を聴くためのコンバータも各種見受けられます。
手作り受信機の可能性
本書には1934年のリプリントに加えて、これから短波ラジオを手作りしてみようという人のための記事があります。
T.J.Lindsayによるこのコーナーでは、真空管式・トランジスタ式・FET式の再生式受信機の回路例が掲載されており、作り方のヒントや作品例の写真もあります。
さらにLindsay氏は、お気に入りの記事としてさらに2つの記事のリプリントを掲載しています。
一つ目はアメリカのCQ誌1966年2月号に掲載された0-V-1受信機、
もうひとつは1942年のARRL Radio Amateur's Handbookからシンプルな1球再生式受信機。
CQ誌の0-V-1は、日本のSWL、JA1-3477 Hijame Suzuki氏(Hajimeさんのミスタイプでしょう) 製作によるもの。
6AU6による再生検波、6AV6による低周波増幅の0-V-1構成でクリスタルイヤフォンで聴きます。
バンド切替はプラグインコイル式、フロントパネルには大型のバンド スプレッド バーニア ダイヤルを持ち、
B電源はVR150により安定化されています。
Suzuki氏はこの小さな手作り受信機と天井に張った10mのワイヤーアンテナで、なんと202カントリーを受信し、176カントリーをコンファームしました。
この成果には世界中のハムも驚き、ぜひ回路図を送ってくれと何件もの問い合わせがあったそうです。
Suzuki氏は記事中で 「回路図だけでは私の受信機の性能は出せません。 特にコイルの巻き方に大変努力して工夫したのです」と述べています。
風でアンテナ線がゆれて受信が不安定になるのを防ぐためにあえて室内アンテナを利用するなど、氏の努力には実に感嘆します。
まさに手作りの小さな受信機の可能性を極限まで追及した例です。 すごい・・・!
とてもSuzuki氏にはかなわないだろうけれど、自分ももう一度0-V-2を作ってトライしてみたくなりました。
さらなる未知の領域へ
この本には当時の受信機の製作記事だけではなく、短波に関連するいくつかの当時の記事も掲載されています。
そのうちのひとつは、1933年の宇宙電波の発見。
ベル研究所
のカール・G・ジャンスキー博士は、
超高感度の短波受信機とビームアンテナをテストしていて、
天空のある方角から周波数20.5MHzの雑音電波が来ていることに気がつきました。
ほぼ1年間にわたり到達方向を調査した結果、電波は銀河中心の方角から来ていると結論されました。
電波天文学の始まりです。
さらにもうひとつの興味深い論文は編者の一人Hugo Grensbackによって書かれた
「我々は惑星と通信できるだろうか?」。
この時代、人類は誰一人として地球大気圏から出ていませんでした。
また学者は、地球はヘビサイド層にとり囲まれているので、電波はヘビサイド層から脱出することはできない、と主張していました。
しかし著者は、以下のように書いています。
|
|
・・・・電波は波長が短くなれば光と区別がつかなくなる。
そして、我々は実際に太陽や月や星を見ることができるのだから、
波長がさらに短くなれば電波はヘビサイド層を突き抜け、地球外の天体にも到達するはずだ。
ヘビサイド層を突破できる波長が5メートルなのか5センチメートルなのか5ミリメートルなのか、誰にも分からない。
誰も試したことがないからだ。
となれば、アマチュアの出番だ。
ちょっと前までは、たかだか5ワットで地球の裏側と通信できるだなんて誰も信じていなかった。
もし適切な周波数が見出せれば、案外100ワット程度で月面反射通信が可能になるかもしれない。
遅かれ早かれ、人類が宇宙船で地球を飛び立つ日が来る。
その時までには、その宇宙船と地上とではたして通信できるのかどうか、答えが出ているだろう。
|
|
いまや我々は日常的に通信衛星を使っているし、月面反射通信を楽しむアマチュア無線家も少なくありません。
人類は月面で飛び跳ねる宇宙飛行士の姿を生中継で見たし、遠く太陽系外縁にまで到達した惑星探査機に司令を送り、
また探査機の小さなバッテリーパワーで動作する送信機からの電波を通じて未知の世界の映像を垣間見ました。
DXリスナーの究極の冒険は、やはり地球外生命からの知的メッセージの受信、ということになるのでしょう。
SETIプロジェクトはそう簡単には成果を出せそうにありませんが、いつかそのうち、はるかかなたからのCQ DXを受信できる日がくるかもしれません。
Go to Books That Stack
Go to NoobowSystems Lab. Home
http://www.noobowsystems.org/
No material in this page is allowed to reuse without written permission.
NoobowSystems has no business relationships with the companies mentioned in this article.
Copyright (C) NoobowSystems Lab. Tomioka, Japan 2002, 2004
May. 06, 2002 Created.
Aug. 17, 2002 Reformatted.
Sep. 07, 2004 Reformatted.



